【保育士監修】パパに1番やって欲しい|子どもの寝かしつけ方法を完全解説

子育てに関する悩みは尽きませんが、特に「寝かしつけ」についてお悩みを抱えているご家庭は、とても多くいらっしゃいます。
なかなか夜に寝てくれない赤ちゃん、イヤイヤ期の1・2歳児…毎日ママが一人で寝かしつけることはとても大変です。
実際に「パパが寝かしつけてくれたら助かるんだけど…」とママから相談された経験はありませんか?
そんなときに、パパが「今日の寝かしつけは俺がやるよ!」とスムーズに寝かしつけてくれたら、とても頼もしく感じます。
実は“ママがパパに任せたい育児“で一番多いのが「寝かしつけ」です。
パパが寝かしつけを担当することで、その間にママは他の家事や通園準備などができるようになり、夫婦のゆとりにも繋がります。
普段、仕事で忙しいパパにお子さんとの貴重な親子時間を楽しんでほしいというママの願いも込められています。
今回は2児の母であり、保育士でもある筆者が寝かしつけの基本的な流れやポイントをまとめていきます。
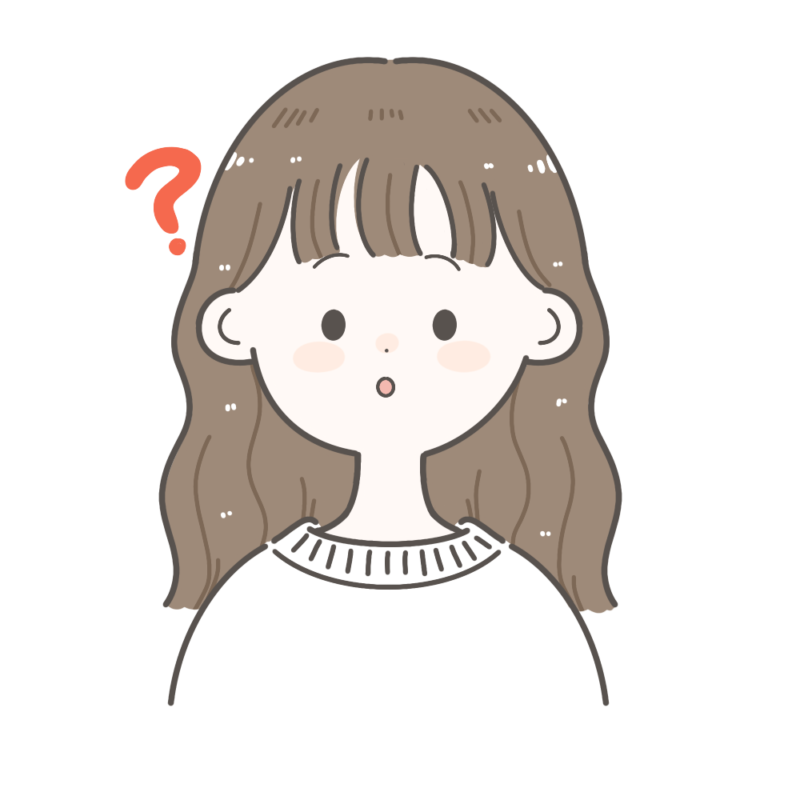
いつもパパの寝かしつけだと泣いちゃうけど大丈夫かしら?

大丈夫!この記事を読んで「寝かしつけはパパの出番!」ってくらい得意になってみせるよ!
寝かしつけは育児初心者のパパでもチャレンジしやすいコツやポイントがたくさんあります。寝かしつけに関する情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
寝かしつけが大切な理由と効果
寝かしつけとは?
寝かしつけとは、お子さんが自然に眠りにつけるよう環境を整えたり、入眠できるよう気持ちを落ち着かせてあげることです。
単なる“眠るまで付き添うこと”ではなく、お子さんの成長や情緒の安定、親子の信頼関係にとても大切なコミュニケーションです。
安心感を持って入眠することで、質の高い睡眠がつながり、お子さんの健やかな成長を促すことができます。
- 抱っこでゆらゆら
- 添い乳(母乳を飲みながら眠る)
- 添い寝(隣で一緒に過ごす)
- ベッドに寝かせてトントンや子守歌
- おやすみの挨拶後に部屋を出る(ねんねトレーニングで使われる方法)
寝かしつけに成功するメリット
寝かしつけがスムーズになると、寝る時間がいつも同じになり、起床時間も定まります。
結果、生活リズムが安定して朝もスッキリ起きられるようになったり、日中機嫌よく活動できるようになったりと、たくさんのメリットがあります。
毎晩同じ手順で安心して眠りにつくことでお子さんの情緒も安定し、自立心の芽生えにも繋がっていきます。夜中に目が覚めても自分で再び入眠する力も育ちます。
保育園に通園の際も、昼間の活動が活き活きとしたり、お昼寝の時間もスムーズに入眠できるなど、良いことの連鎖が続きます。
寝かしつけに失敗するデメリット
お子さんの健やかな成長にとって、”睡眠”はもっとも大切です。
睡眠時間が不足することにより、気持ちが不安定になり、自立心が育ちにくくなります。
また、入眠に時間がかかることで、パパやママの十分な休息時間が確保できず、共に疲弊してしまいます。
慢性的に続くと、日常生活に支障が出てしまい、お子さんと向き合うことが徐々につらくなってしまいます。
寝かしつけが上手くいかないことは、家族にとってデメリットがとても大きいのです。
寝かしつけはパパにして欲しい理由
ママの負担軽減に直結する
子育ては想像以上に体力も精神力も使います。
特に赤ちゃん時期は、夜間授乳、ママへ後追い、夜泣きの対応もあり、常にヘトヘトになっていることも多いでしょう。
寝かしつけをパパに任せることができれば、毎日少しでも安らぐ時間を持ち、心身をリセットすることができます。
親子時間を大事に過ごしてほしい
ママは、大好きなパパと我が子に良好な親子関係を築いて欲しいと心から願っています。
入眠前は、お子さんが一日の中で最もリラックスしている時間。
お子さんとゆったりした時間を過ごすことで、親子の絆をさらに深めることができますよ。
限られた時間を有効活用できる
パパが寝かしつけをしてくれている間、ママは家事や通園準備などを効率よく行うことができます。
日中はお子さんがいると家事がうまく進まない…ということがよくあります。お子さんを意識しなくても良い環境で、頭の中ではやりたいことがたくさん!自分のペースで少しずつでも進められる時間を作ってあげてくださいね。
寝かしつけはパパが向いている理由
パパの冷静な寝かしつけは相性抜群
ママは”私じゃなきゃダメ””私が頑張らないと”と、子育ての悩みを抱え込んでしまいがちです。
寝かしつけにおいても、上手くいかなくて焦ったり悩んだりという気持ちがお子さんに伝わってしまい、余計に寝付けなくなってしまう負のループに陥ることも。
個人差はありますが、パパの方が感情的にならず冷静さを保ちやすいため、寝かしつけに向いているという傾向にあります。
お子さんにとっても、パパの低く落ち着いた声や、大きくてがっしりとした手や身体は、ママとはまた違うとても心地の良い刺激となります。パパならではの安心感を受け、お子さんの入眠もスムーズになります。
時間的に役割分担がしやすい
パパが寝かしつけを率先して行うことで、ママの負担が減り、夫婦にゆとりが生まれます。慢性的な疲労はイライラの根源。夫婦で協力して、健康的な生活を送りながら子育てしていくためにも、ママの体調も支えていきましょう。
普段、日中は仕事でお子さんとの時間がないパパでも、入眠前の穏やかな時間を一緒に過ごすことができます。親子の信頼関係も深まり、パパにとってもかけがえのない時間になります。
パパが寝かしつけを日常的にやってくれることで、お子さんはママに依存せず「いろいろな人に愛されているんだ」という自覚を持ち、自己肯定感を育むことができます。
お子さんの成長基盤ともなりますので、ぜひ大切にしていきたいですね。
ここからは、具体的な寝かしつけの進め方について解説します。たくさんのポイントがありますので、ゆっくりとご覧ください。
寝かしつけの基本手順・コツ
寝室環境を整えよう

正しく寝室環境を整えることで、快適な入眠に繋がります。次のようなポイントに合致する場合は見直しのチャンスです。
- 家電製品のわずかな明かりや、カーテンから光の漏れはありませんか?
- 暑すぎず寒すぎない心地のよい温度・湿度になっていますか?
- 余計な刺激となるおもちゃやタブレットなどを持ち込んでいませんか?
早起きすぎて困っているお子さんも、寝室環境を見直すことで朝までぐっすり眠ってくれるようになりますよ。
寝かしつけに最適な寝室環境については、こちらで詳しく解説していますので、是非チェックしてみてください。
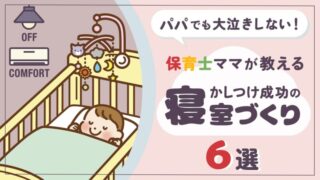
入浴(沐浴)と保湿でリラックス

「寝かしつけにお風呂?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は入浴と睡眠は深い関係にあります。
皆さんもお風呂にゆったりと浸かったあとに髪の毛を乾かし、しばらくするとウトウト眠気が…なんてご経験はありませんか?
大人も子どもも、体が温まってから約1時間くらいかけて体温が下がってくると、心地よい眠気に誘われるようになります。
そのため、就寝の約1時間前にお風呂に入るよう調整すると、スムーズに入眠しやすくなります。普段はシャワーで済ませるというご家庭もありますが、寝つきにお悩みの方はぜひ1度お試しください。
お子さんとゆったりお風呂に入りながら、今日の出来事について会話を楽しんだり、スキンシップを取ることで安心感を得ることも重要です。
入浴後はたっぷりと保湿してあげましょう。
皮膚の乾燥による痒みでなかなか寝付けなかったり、夜中に起きてしまったりするお子さんもいます。身体の状態を整えてあげることも良質な睡眠に繋がります。
最近では、リラックス効果のある保湿クリームなども赤ちゃん・お子さん向けに販売されていますので、効果を確認してみるのもおすすめですよ。
沐浴と保湿のポイントは、こちらで詳しく解説していますので、是非チェックしてみてください。

授乳・水分補給も忘れずに

入浴後は喉が渇くので、おっぱいやミルク、お水や麦茶など水分補給をしましょう。
温かい湯舟につかりリラックスしたあとは、大好きなパパママに抱っこされて授乳することで、より安心感を得られますね。特にパパにミルクをあげてもらうことで、赤ちゃんもパパへの信頼感がさらに増し、特別な時間になることでしょう。
お水や麦茶など、お子さんのトイレ事情に合わせ、量を調節して飲ませましょう。
授乳に関してのポイントは、そのまま寝落ちさせないように注意することです。赤ちゃんの中で「授乳=ねんね(入眠儀式)」になってしまうと、入眠時におっぱいや哺乳瓶が無いと眠れなくなってしまうことが多いです。
特に保育園に預ける予定がある方は、授乳と入眠を切り離しましょう。おっぱいがないとお口が寂しくて眠れないお子さんは、園生活に慣れるまで時間が掛かってしまい、お子さんの負担になってしまうこともあります。
パパの授乳サポートやミルクの作り方は、こちらで詳しく解説していますので、是非チェックしてみてください。

歯磨きでお口スッキリ

お子さんの月齢・年齢に合わせて歯磨きを行いましょう。
水分補給後に歯磨きをすることで、虫歯予防や着色予防になります。
乳歯が虫歯になると口内環境が悪化し、様々な悪影響を及ぼします。決して、乳歯は抜けるから大丈夫と思わず、大切に磨く習慣を付けてあげましょう。
歯磨きに関しても、「パパだと嫌がってしまう」「泣いて上手く仕上げ磨きができない」などお悩みも多いですよね。
「お風呂に入って水分補給したら歯磨きしようね!」と伝えながらルーティン化することで、先の見通しが立ち、スムーズに歯を磨いてくれるようになりますよ。
歯磨き(仕上げ磨き)はパパの関わり・アイデア次第でとっても楽しい時間になります。
歯磨きのポイントや効果的な声掛けなどを詳しく解説していますので、あわせてこちらの記事をご覧ください。

オムツの交換・トイレを促そう
寝室に行く前にオムツのチェック、トイレの促しを行いましょう。
お子さんによっては、ほんの少しオムツにおしっこが出ているだけで不快に思って寝つけなかったり、泣いてしまうことも。夜間に長時間着用するので、肌荒れ予防のためにも清潔な状態で入眠できるようにしましょう。
トイレトレーニング中のお子さんは、「寝る前にトイレで座ってみようね!」と日々声を掛けることで習慣化しやすくなります。
保育園でも「トイレ・オムツ交換」と「お昼寝」はワンセットです。お子さんは先の見通しが立つと安心し、気持ちを切り替えやすくなりますよ。
トイレトレーニングの進め方については、こちらで詳しく解説していますので、是非チェックしてみてください。

絵本を読んで心を通わせよう

お風呂から一通りの生活習慣のルーティンが終わったら、いよいよ寝室へ。
ゆったりとした雰囲気の中、絵本の読み聞かせを行いましょう。寝る前に絵本を読むことで、次のような良い効果があります。
- 親子の対話 → 安心感や癒しを得る
- 就寝前の絵本 → 語彙力・想像力が育つ
- 絵本のあとは眠る → 先の見通しが立つ
0歳の赤ちゃん時期でも、絵本の読み聞かせは癒しやリラックス効果がありますので、ぜひ月齢に合わせて読んでみてくださいね。
絵本は寝かしつけの時以外でも、お子さんの豊かな心を育む大切なコミュニケーションツールです。
保育士である筆者が、読み方の実践方法や絵本の選び方を詳しく書いていますので、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

電気を消して寝かしつけよう
寝室の明かりを消したら、いよいよ寝かしつけの時間です。
【赤ちゃん】抱っこでゆらゆら眠るモード
月齢の短い赤ちゃんや、敏感な子には抱っこで”ゆらゆら揺れ”が効果的。
抱っこ紐やスリングを活用すると、身体の負担も軽くなりますよ。
実は、赤ちゃんは上下に揺れると心地よさを感じ、眠りにつきやすいことが分かっています。
我が家でも大活躍したのが「バランスボール」
抱っこ紐で抱っこして、バランスボールに乗って上下に揺れると、驚くほど負担なく寝かしつけができるのでおすすめです。
午前睡・午睡・就寝時間のリズムがついてきたら、抱っこから添い寝へ移行していきましょう。
保育園においても、入園当初は抱っこでウトウトするまで眠気を誘い、その後にベビーベッドへ移動します。泣いてもしばらく様子見を繰り返して、少しずつ慣らしを行います。
布団で眠りに付けるようになると負担もグッと減り、赤ちゃんの眠る力がぐんぐん育ちます。
添い寝とトントンで安心感
お子さんによって、触れられると眠りやすいところや、心地のよいリズムなど違いますので、ぜひいろいろ試してみてくださいね。
保育士として数多くのお子さんの寝かしつけに携わる中で得た「おすすめの寝かしつけ方法」はこちらです。
- 背中や胸、おなかを優しくトントンする(強弱やリズムはお子さんの好みによって変えましょう)
- 足をさすってあげる(だんだん眠くなって足があたたかくなってきます)
- 手を握ってあげる
- おでこや眉をなでる(左右に動かしたり、くるくる円を描いてみたり)
- 腕枕をしてあげる
- 髪の毛を優しくなでる
我が家の子どもたちは、トントンやなでると気になってしまうタイプのようで、「腕枕」で体を密着することでコロンと寝てしまいます。様々なタイプのお子さんがいるのも面白いですよね。
保育士おすすめの添い寝・トントン必勝法については、こちらで詳細に解説しています。今晩からやってみよう!と思うたくさんのコツがありますよ。
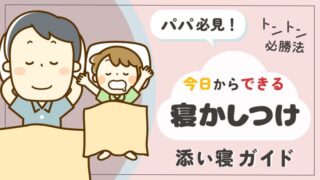
月齢・年齢別|寝かしつけで押さえるポイント
月齢や年齢により、寝かしつけのポイントや日々のルーティンは異なります。
一日のほとんどを寝て過ごす新生児から、一緒にお風呂に入れるようになり、乳歯が生えて歯磨きが始まり、トイレに座るようになり…。
日々成長しているお子さんに合った寝かしつけまでのステップをたどることで、よりスムーズな入眠に繋がります。
お子さんの発達状況に合わせた寝かしつけのルーティンは、こちらで解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

新生児~3カ月│抱っことリズムがカギ
まだ昼夜の区別がついておらず、ルーティンを意識しすぎる必要はありません。
まずは、安心して心地よく眠れるようサポートしてあげましょう。
赤ちゃんはお腹の中と似た環境や、声・音・リズムに安心感を覚えます。
軽く揺れる抱っこや、おくるみで包んであげるなどが効果的でしょう。
赤ちゃんによって、縦抱き・横抱きの好みがありますので、いろいろ試してみてくださいね!
4カ月~6カ月│生活リズムを整えていこう
少しずつ昼夜の区別がつき始めます。
ルーティン生活を取り入れていきましょう。
赤ちゃんは毎日決まったルーティンを繰り返していくと、「次は○○」と見通しを立てることを覚えて、すんなり眠れるようになります。
ルーティンを意識的に作りましょう。
①入浴・保湿 → ②授乳 → ③オムツ交換 → ④絵本 → ⑤寝かしつけ
同じ手順を、同じ時間帯に繰り返すことが重要です。
7カ月~1歳│夜泣き・後追いがピーク
夜泣きや後追いがピークになります。
パパとママで交互に対応したり、役割分担をするなど、協力して乗り越えましょう。
添い寝とトントン・言葉掛けを行います。
「パパはここにいるからね」「大丈夫だよ」など、安心できる言葉を掛けてあげましょう。
ハイハイやつかまり立ちを始める時期です。日中はたくさん遊ぶことで、心地よい疲労感から入眠もスムーズになります。
1~2歳│イヤイヤ期にもルーティンが効果あり
自己主張が始まり、イヤイヤ期突入!
お子さんの気持ちを尊重しつつ、いつものルーティンへ誘導するのがコツ。
語彙力も高まり、言葉のやり取りが楽しくなる時期になりますので、絵本の世界もより広がります。
寝かしつけ前に、トイレへ誘うルーティンを組みましょう。
イヤイヤ期は、お子さんに選択肢を与え、最終決定を任せてあげるのがポイント。
「絵本どれ読みたい?」「自分でお布団行く?それとも抱っこで行く?」「歯磨き自分で持つ?パパが持つ?」など、お子さんへ問いかけを意識してみましょう。
3~5歳│自分で眠る力を育成
「自分で眠りに向かう力・眠る力」を少しずつ育てていきたい時期です。
「自分から何かしてみたい!」と自発性が育つ時期なので、次に何をしたらよいか、自分で考えられるような声掛けをすると良いですね。
「歯磨きのあとはトイレに行ってから布団に入る!」と自発的にルーティンに沿って行動できるようになります。
まだまだおうちの方に甘えたい年頃ですので、必ず一人で眠れるようにする必要はありません。添い寝で安心感を得ながら、眠る力を育てていくイメージで進めましょう。
親子で向き合う時間を大切にしましょう。
出来ることが増え、心身共に急成長する時期ですので、眠る前の会話は心の変化に気が付くきっかけにもなります。
寝かしつけが長引く理由・対策
事前準備が不足している
寝かしつけの基本を振り返り、準備を万全にしよう
保湿が不十分で身体が痒かったり、授乳が不十分でまだ喉が乾いていたり…寝かしつけ前のルーティンが不足すると入眠に影響が出ることもあります。
基本手順を振り返り、再確認を行いましょう。
お風呂あがりの授乳・水分補給が不足している場合や、オムツが濡れている・トイレに行きたい場合が多い傾向にあります。
手順がいつもと異なる
同じ時間・同じ流れのルーティンを!
お風呂に入れなかったり、絵本を読めなかったりする日もありますよね。
いつもの基本手順であるルーティンを飛ばしてしまっている場合に、違和感を感じて眠りに付けないこともあります。
特に赤ちゃんは、いつもと同じ時間・同じ手順を意識することが重要です。
当日の体調や都合などで手順が前後したり、飛ばしてしまったりすることもありますよね。
「今日はいつもと流れが違ったから寝つきが悪いのかな?」と原因の一つとして考えておくと、気持ちもラクになりますよ。
寝室環境が整っていない
明かり・音・温度・湿度を要チェック!
寝室が明るすぎていたり、暑かったり寒かったり…お子さんは環境に対して微妙な違和感を感じます。
寝室環境を今一度見直してみるのが大切です。
気になる明かりはないか?温度や湿度は快適か?いつもと違う落ち着かない音がしないかなど要チェックです。
寝かしつけは夫婦のチーム力がカギ!
役割分担を決めよう
パパとママで役割を分担することで、寝かしつけがよりスムーズになります。
- パパは、お風呂・絵本・添い寝 の担当
- ママは、着替え・保湿・授乳・歯磨き の担当
※ 各曜日で組み替えるのも良いでしょう。
シンプルで分かりやすい分担を決めると続けやすいですよ。
ただ、完全に役割を固定するのではなく、疲れているときなど臨機応変に交代できるように心掛けておくと気持ちよく助け合えますね。
情報を共有しよう
寝かしつけはスムーズな日もあれば、長引いてしまう日もあります。
上手く眠れた日も、眠れなかった日も、パパママ揃って「お疲れ様」の気持ちを持つことが大切。それと同時に、失敗や成功の情報共有も行えるといいですね!
「昼寝の時間が長すぎたかな?」・「昨日は○○をトントンしたらすぐ寝られたよ」など寝つきの状況を共有しておくと、どちらが寝かしつけを担当してもスムーズになりますよ。
ルーティンを固定しよう
パパとママで同じような言葉掛けや、ルーティンの手順を踏めるようにしましょう。
特に赤ちゃんは同じ生活リズムで過ごすことで安心感を得ることが出来ます。
どちらが担当しても、同じ時間に同じ手順で過ごせると寝かしつけはスムーズに進めることができます。
寝かしつけで心地の良い親子時間を…

以上、寝かしつけのまとめとなります。
お子さんにとって睡眠は大切であると分かっているからこそ、深く悩んでしまいますよね。
寝かしつけは”添い寝”だけではなく、寝室環境を整えたり、お風呂に入るタイミングから始まっています。さらに日中の活動量や起床時間、午睡時間などすべてが関係しているとも言えますね。
寝かしつけ対策は、生活習慣の様々な悩みの解決にも繋がっていきます。
パパが熱心に育児の悩みを解決しようと模索する姿は、ママ目線から見ると、とても頼もしく、ともに子育てを頑張っている!と感じられます。
普段の何気ない会話の中で、「最近〇〇が大変だよね。解決策調べてみたんだけど…」とぜひママに共有してみてください。
夫婦で協力してお互いを思いやりながら、子育てに取り組んでいきましょう。
