今日から始める|パパの添い寝&トントンでスムーズに寝かしつけるコツを保育士が解説
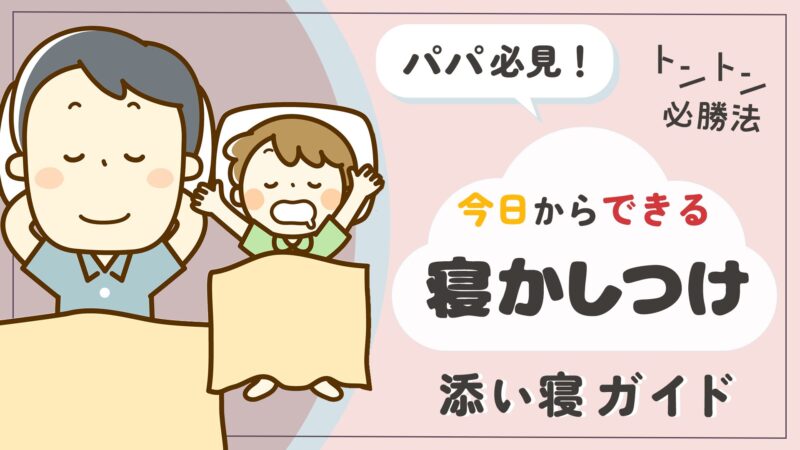
寝かしつけは、スムーズに眠れる子もいれば、入眠するまでに一泣きしてから、絶対ママじゃないと眠れない…などお子さんによって様々です。
寝かしつけには寝室環境を整えたり、絵本を読んで気持ちを落ち着かせたりという前段階を踏まえることでスムーズになります。
しかし…こんなパパも多いのではないでしょうか。

楽しく絵本も読めたし、いざ寝かしつけるぞーっ!と電気を消したら「ママがいい~」って大泣き。パパも寂しいよ…
絵本までは読めても、いざ寝ようとすると泣いたりパパを嫌がったりするお子さん、実はとても多いんです。我が子もそうでした。
ここでは現役保育士ママである筆者が寝かしつけの添い寝・トントンするときのポイントに焦点を当て、徹底解説していきます。
今晩から試せることばかりなのでぜひ実践してみてくださいね!
寝かしつけ全般の進め方についてはこちらでまとめていますので、あわせてご覧ください。

添い寝ってなに?

添い寝とは、お子さんの横で一緒に寝ながら、眠りへと導いてあげる魔法の寝かしつけのことです。
- 抱っこで寝かしつけ
- 添い乳で寝かしつけ(母乳を飲みながら眠る)
- ベビーベッドに寝かせてトントンや子守歌
- おやすみの挨拶をしたら親は部屋を出ていく(通称ネントレで使われる方法)
添い寝での寝かしつけは、パパのぬくもりを感じながら安心して眠りにつけるため、信頼関係も深まるという大きなメリットがあるのが特徴です。
パパが添い寝する効果
パパが寝かしつけで添い寝をすると、どんなメリットがあるのでしょうか。
具体例をご紹介していきます。
パパのぬくもりで安心感を与える
声が低く、身体も大きくて包容力のあるパパとの添い寝は、ママとはまた違う安心感があります。大好きなパパと、肌と肌の触れ合いを感じることで安心することができ、よりスムーズな入眠へと繋がります。
パパとの信頼関係が育まれる
添い寝はただ横に寝るだけではありません。
添い寝中のスキンシップや言葉掛けは親子の絆を深める良いチャンスです。
小さいお子さんはただ横にパパが居てくれるだけで安心します。大きいお子さんにとってはパパと一日を振り返ったり、日々の感謝を伝えあったり、かけがえのない時間になります。
そんな時間の積み重ねが親子の信頼関係を深めていくのです。
ママの負担を軽減できる
寝かしつけをパパが担当してくれることで、ママは他の家事に専念できたり、ホッと自分時間が過ごせたりと時間の有効活用が出来ます。
大変な寝かしつけをパパが率先して引き受けてくれることで、パパからの思いやりを感じることができ、夫婦で協力して子育てに向き合うことができるようになりますよ。
異変にすぐに気付ける
お子さんのすぐ隣に添い寝することで、お子さんに体調の変化があった場合すぐに気付くことができます。身体の異変はもちろんのこと、一日の終わりに隣にいてあげることで心の変化にも気づけますよ。例えば、今日は悲しいことがあった様子で落ち込んでいる。何か悩みがある様子でいつもと様子がおかしい…など。
体調や心の変化も見過ごさずに気付いてあげることができます。
添い寝&トントンで眠れる子は入園後もスムーズ
筆者は保育現場で働いていますが、4月によく聞くご家庭の悩み。
それは「うちの子、家で抱っこでしか寝ないんです。」
特に0・1歳児は、抱っこで寝かせてそっとベッドにおろす、という流れで寝かしつけをしているご家庭は多いです。
入園後の慣れない環境で、眠くなってしまったときお子さんは大泣きをします。
最初の数週間は保育士と赤ちゃんの信頼関係がまだできていないため、安心感を持ってもらえるよう抱っこします。ウトウトしたらお布団やベビーベッドに寝かせトントン。
ほとんどのお子さんがおろした瞬間に大泣きをしますが、すぐに抱っこするのではなく、トントンしたり、声を掛けたり、手を握って少し様子を見ます。
それでも大泣きなら抱っこで寝かしつけます。この一連の流れを日々繰り返し、少しずつ、少しずつお布団で入眠できるようにしていくのです。
ご家庭で添い寝やトントンで眠る習慣ができている赤ちゃんは、園生活で眠れるようになるのも比較的スムーズです。自分で入眠する力が育っているからですね。
寝かしつけ=授乳になっている赤ちゃんは慣れるまで特に一苦労します。
お口に何かくわえていないと寝付けない習慣になっていると、入園してから安心して眠れるようになるまで時間が掛かる傾向があります。授乳と寝かしつけは結び付けないことも覚えておくと良いですよ!
お子さんのためにも、少しずつ抱っこではなく添い寝で眠れるよう促していけるとよいですね。
良く寝る添い寝のポジションは?
添い寝する場所もお子さんによって好みが様々あります。
お子さんのどこに寝るか、実は重要なポイントのひとつとなります。
同じ向きで横に寝るのが基本
基本的には、お子さんの隣に同じ向きで横になるのが主流です。
兄弟・姉妹がいる場合は、パパが真ん中になり両脇にお子さんたちを寝かせてあげると、寂しい思いになりません。
お子さんによって背中側派・向かい合う派も
お子さんによっては、パパに背中を向けて寝ることで安心できる子もいます。子どもながらに、「背中側は見えないからなんだか怖い」と感じる子も。
向かい合ってパパの表情や吐息を感じることで安心できる子もいます。
筆者は保育園で働いていますが、お子さんによって寝やすい姿勢は様々です。
大の字になって寝付く子もいれば、保育士の方に向かいあって寝る子、保育士に背を向けて寝たい子など。
窒息の可能性から推奨はしていませんが、寝付くときはうつ伏せを好む子もいます。
よく観察して、お子さんの寝付きやすいポジションや姿勢を掴めると良いですね。
添い寝で使える言葉掛けとタイミング
添い寝するときに有効なのは、優しい言葉掛けです。
大好きなパパの優しい声でより入眠もスムーズになることでしょう。
落ち着く言葉掛けで安心感を
入眠前の言葉掛けは、ささやくような声の大きさで、落ち着いたトーンで話しましょう。肯定的で、穏やかな言葉を選び、安心感を与えるのを意識しましょう。
話し掛けすぎると、返って入眠の妨げになってしまうので、ほどほどに。
眠そうになってきたときにそっと声掛けを
タイミングは、なんだか眠そうになってきたときにそっと言葉を掛けましょう。
逆に、まだ眠そうにない場合には話し掛けるのはやめます。
おすすめの言葉掛けの具体例
- 「パパはここにいるからね」
- 「トントンしようね」
- 「今日もいっぱい遊んだね」
- 「生まれてきてくれてありがとう、大好きだよ」
- 「おもちゃもみんなねんねしてるから、一緒に寝ようね」
など、肯定的で安心できるような言葉掛けを意識しましょう。
やりがちなNGな言葉掛け
- 「もう早く寝なさい」
- 「何で全然寝ないの?」
- 「もう寝る時間だよ」
- 「寝ないと鬼が来ちゃうよ」
など、お子さんを追い詰めるような言葉掛けは絶対にやめましょう。

言葉掛けってどんな風に言ったらいいのか分からなかったけど、肯定的で穏やかな言葉を選べばいいのか!
早速、今日の寝かしつけから始めてみるよ。
添い寝トントンの必勝方法
添い寝とセットでよく行われるのは「背中トントン」です。
保育士的には、「トントン」は寝かしつけの必勝テクニックでもあります。
リズムは呼吸に合わせてゆっくりが基本
お子さんの呼吸や心拍に合わせて一定のリズムでトントンします。
特に赤ちゃんが「トントン」で安心する理由は、ママのお腹の中にいたときの記憶に近い為です。ママ体内では、心臓の音や血流の音など一定の音が永遠と続いてます。
一定に続いているリズムを「トントン」で再現することで、赤ちゃんはお腹の中を思い出し安心します。その結果スムーズな寝かしつけに繋がるのです。
基本的にはゆっくりなテンポでトントンするのが効果的ですが、お子さんによってはソフトタッチで軽快なテンポを好む子もいます。お子さんに好きなトントンを聞いてみたり、日々の寝かしつけで好みを掴めると良いですね。
優しく触れよう
力加減は優しくソフトに。
強すぎるトントンはかえって刺激になってしまい、入眠の妨げになります。
ママの鼓動を表現するようなイメージで優しく、一定のリズムを心掛けましょう。
背中・頭・お腹・足などお子さんの好みで
- 背中やお腹を優しくトントン・撫でる
- 髪の毛を優しくトントン・撫でる
- くるぶしを丸く撫でる・さする
- 足を優しく太ももからふくらはぎに掛けて撫でる
- おでこ・眉毛を優しく撫でる・丸くなでる
- 手を握る・揉む
筆者が保育士として働く中で、お子さんによって落ち着くトントンは様々でした。
赤ちゃんの頃は、頭に吐息を掛けると落ち着く子もいましたよ!
眠そうな仕草を見逃さないで

保育現場でもよく見られる、お子さんが眠くなった時のサインをご紹介します。
あくびや目をこする
最も分かりやすいサインですね。
繰り返すようなら、眠気が強い証拠です。
言葉数が減る
さっきまであんなによくしゃべっていたのに、急に静かになったら、眠気のサイン!
ぼーっとする
集中力が低下し、話し掛けても反応が遅くなります。
ぼーっとしたら眠い証拠です。
耳や髪の毛を触ったり指をくわえる
眠いときに自分で自分を落ち着かせるために、耳や髪の毛を触るお子さんも多いです。
親指を口にいれて指しゃぶりをしたり、手を口に入れたりするのも眠くなっているサインです。
添い寝中に心掛けてほしいポイント・コツ
スムーズにいかないことも多々ある寝かしつけ。
パパが寝かしつけを担当するうえで、心掛けてほしいポイントをご紹介します。
無理に寝かせようとしない
「早く寝てほしい」という気持ちはよく分かります。
お子さんの生活リズム的にも早寝は大切ですし、パパ的にも寝かしつけ後にやらなけばならないことや、やりたいこともありますよね。
しかし、「早く寝てほしい」気持ちがお子さんに伝わると、返って寝つきが悪くなります。むしろ急がず、おおらかな気持ちで添い寝していると、案外コロっと寝てしまうこともあります。
心構えとしては、「寝かせる」よりも、「パパも一緒にくつろいじゃおう」というスタンスに変えてみると良いですよ!
スマホをいじらない
スマホの光や音により、お子さんを覚醒させてしまいます。
添い寝中、スマホは触らず、通知音もオフにしておくと良いでしょう。
寝る前にテンションを上げないように
寝る前に興奮してテンションが上がってしまうと、クールダウンに時間が掛かります。
絵本やパパとの穏やかなお話で気持ちを落ち着けたら、そのまま消灯して添い寝に入るようにしましょう。ついつい可愛くてこちょこちょや楽しい触れ合い遊びをやりたくなってしまう気持ちも分かりますが、入眠前は控えましょう。
寝なくてもイライラしない!一旦リセットも効果的
消灯して1時間も経過したのにまだ寝ない…
そんな日もありますよね。「明日も保育園だし早く寝かせてあげなきゃ」というのも親心ですが、身体を横にするだけでも脳も身体も休まります。
それでも、焦る気持ちやイライラが出てきてしまったら、一旦明かりをつけてみましょう。寝室から出て、トイレにいったり、お水を飲んで5分ほど一呼吸。その後、また寝室で添い寝してみると、意外にもスムーズに寝付くケースもありますよ!
筆者は、我が子がなかなか寝付けないときにこの手をよく使います。
子どもながらにも、「早く寝なきゃなのに眠れないよ…どうしよう…」という気持ちや焦りがあるのでしょうね。
環境の見直しも必要
なかなか入眠出来ないときには、再度、寝室の環境を見直すことも大切です。
明かり、音、気温、湿度など、子どもはわずかな刺激に敏感です。
寝室環境の見直しポイントについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
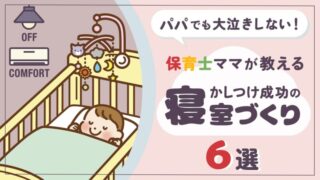
添い寝で寝たのに起きたときのリカバリー方法

お子さんが寝たと思って、起き上がると起きてしまう時もありますよね。
添い寝は安心感を感じられるのがメリットですが、パパが起き上がる際にベッドの揺れや音などで起きてしまう…というデメリットもあります。
慌てず優しくトントン
起きてしまったら、慌てずにまたトントンしてみましょう。
少し起きた程度なら、ゆっくりとしたテンポでトントン。
もし泣きだしてしまったなら、早めのテンポでトントンしてみましょう。
だんだん泣き止んできたら、それに合わせるように少しずつリズムをゆっくりに…最後はそっとトントンをやめます。
トントンしながらパパも起き上がりやすい体制に変えると、ベッドから抜け出すのもスムーズになりますよ。
パパの寝たふりも効果的
パパの寝たふりもかなり効果的です。
一度起きてしまっても、隣で大好きなパパがスヤスヤと眠っているのを確認すると、安心してまた眠りに付けるようになります。

途中で起きちゃっても慌てないのがコツなんだね。
パパの寝たふりも効果的なのか~!寝落ちしないよう気を付けながら早速試してみよう。
【年齢別】添い寝のポイント
「添い寝」といっても、年齢によって注意点、効果的な方法は異なります。
ぜひ、お子さんの年齢に応じてチェックしてみてください。
0歳は窒息に十分注意して
この時期は、最も窒息に注意が必要なので、安全面を第一にしましょう。
うつ伏せ寝や寝返りのリスクから、柔らかすぎる布団や枕、ぬいぐるみなどは置かないようにします。
そして、大人との添い寝は寝落ちしてしまい無意識に赤ちゃんの上に覆いかぶさってしまう可能性があるため、注意が必要です。
添い寝で赤ちゃんを寝かしたあとに、ベビーベッドなどに移せるのであれば問題はないです。
ベッドの隣にベビーベッドをつなげて隣で寝るようにしたり、赤ちゃんの寝るスペースを物理的に仕切るようにしましょう。
近頃は、安心して赤ちゃんと添い寝できるような「ベッドインベッド」(ベッドの上に置く赤ちゃん専用のベッド)や仕切りなども多く販売されているので検討してみるのも良いでしょう。
赤ちゃんが安心して眠れるお部屋作りについては、こちらの記事をご参考にしてみてください。
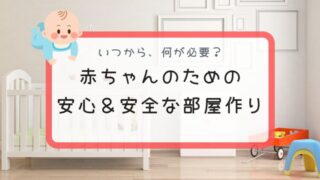
1歳2歳はぬくもりを
自我が芽生えイヤイヤ期を迎えるお子さんも多く、「寝たくない!」「遊んでいたい!」という子や、「ママじゃなきゃ嫌だ!」と自己主張する子もいます。
そんな1、2歳のお子さんには、パパが心にも身体にも寄り添うことで安心できるようにしてあげましょう。
お子さんの言葉には十分に共感してあげたり、寝る際にはぴったりくっついてみたり。
「自分はパパやママから愛されていて、大切な存在なんだ」ということを心の深くで感じられるかどうかが、その後の成長に大きく影響してきます。
3歳4歳は安心できる言葉掛けを
この時期には、想像力が大きく育っています。
「おばけが怖い」「あの影がおばけみたいでいやだ…」など豊かな想像力がゆえに不安になってしまうお子さんも。
あたたかくて安心できる言葉をチョイスし、お子さんが「パパがいるし大丈夫」と思えるようにしてあげられたら良いですね。
逆に、明るい素話でお子さんの想像力を楽しい方向へとつなげてあげると、入眠もスムーズになりますよ!
添い寝っていつまで?5歳以降は添い寝卒業のお子さんも
いつまで添い寝するものなの?と思う方もいらっしゃると思います。
早い子では、5、6歳の小学校入学を機に自分の部屋で寝るという家庭もあります。
無理に添い寝をやめる必要な全くありませんし、逆にお子さんがもう一人で寝たがっているのに無理に一緒に寝る必要もありません。
ひとりで眠る力はとても大切ですが、焦らずお子さんの性格や気持ちに寄り添うことが一番大切ですよ。
長い人生の中で、お子さんから「一緒に寝よう!」と言ってもらえるのはほんの数年…まして添い寝やトントンが必要なのはもっと少ない期間です。
お子さんの希望を尊重して、入眠前の時間を大切にしてあげたいですね。
親子の心地よい添い寝時間を…
- 安心感を与えられるような言葉掛け
- お子さんの好みのトントン
- 「一緒にパパもくつろぐ」心構え
- 年齢別添い寝の留意点
以上が添い寝についての解説となります。

添い寝で寝かしつけって我が子との信頼関係を築く大切な時間なんだね。最初はうまくいかなくても、頑張ってみよう!
寝かしつけ=パパの出番!と思って楽しみながらいろいろ試してみるよ。
はじめは苦戦することもあるかもしれませんが、何より日々の積み重ねが大切です。
これらを踏まえて、ぜひ今晩から親子にとって心地の良い添い寝時間をお過ごしくださいね。
