パパの寝かしつけがもっと上手に!現役保育士おすすめ寝室環境のコツ6選
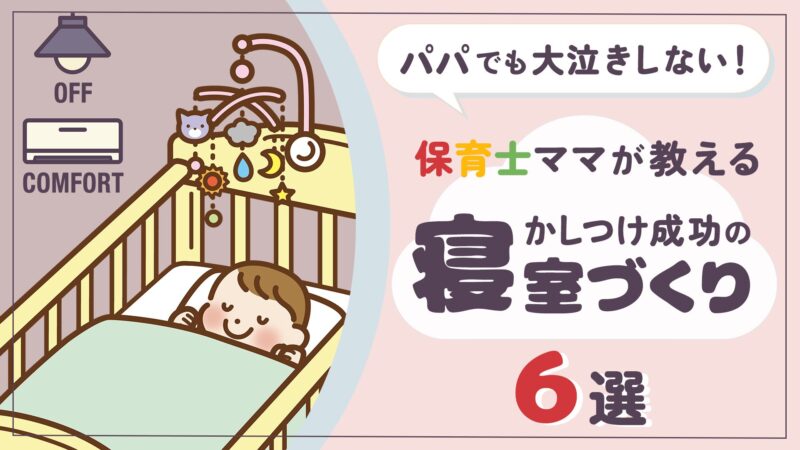
毎日お子さんと向き合っているパパさん、お疲れ様です。
子どもの寝かしつけって本当に大変ですよね。
特に育児にまだ慣れていないパパにとっては、お悩みも多いはず。

眠りにつくまでに時間が掛かってついイライラ…
十分眠そうなのにどうして上手く眠れないんだろう?
何かスムーズに寝かしつけできるような策はないだろうか。
スムーズな寝かしつけには、実は寝室環境が大きく影響しています。
寝室環境を整えてあげるだけで、寝かしつけが劇的にラクになるんです!
私自身も寝かしつけでたくさん悩み、いろいろな策を試してきました。
そんな2児の母でもある保育士ママが寝かしつけ成功のカギとなる寝室づくりをご提案していきます。
入眠しやすい環境を整えることで寝かしつけがスムーズになり、パパも十分な睡眠を確保できたり、自分時間も増やせるようになります。ぜひ最後まで読んでみてください。
寝かしつけ全般の進め方についてはこちらでまとめていますので、あわせてご覧ください。

寝室のライトは消して真っ暗にしよう

常夜灯やスイッチのわずかな明かりが大敵
入眠しやすい寝室環境で特に注意すべきなのは「明かり」です。
とくに赤ちゃんは光の強さに敏感なため、電気や常夜灯がついていると気になって入眠の妨げになってしまいます。目に光が入ると、「メラトニン」という眠りを促すホルモンの分泌が抑えられてしまうからです。
大人の感覚的には、「子どもは真っ暗だと怖がって寝られないんじゃない?」というイメージがあるかと思いますが、脳化学的にも真っ暗な方がスムーズに眠りにつけることが証明されているのです。
心地よい睡眠時間が得られるようになるためにも、できる限り真っ暗な環境を整えてあげましょう。
エアコンや加湿器、空気清浄機などのスイッチのわずかな明かりにも反応してしまうこともあるので注意が必要です。
電気・常夜灯は消し、明かりがついているスイッチは暗い色のビニールテープや、厚紙を貼るなど工夫してみましょう。
真っ暗だと怖がってしまう時は?
1,2歳以降になると「真っ暗だと怖くて眠れない」というお子さんもいらっしゃると思います。
怖がらせてしまうと逆効果になってしまうので、その子の様子に応じて小さなライトを寝入るまでつけてあげたり、徐々に暗い環境にも慣れていけるようにしたりと工夫してみると良いでしょう。
真っ暗にして怖がってしまったらすぐに電気をつけるのではなく、今日の出来事の会話や楽しい昔話を話してみたり、一緒に歌を歌ってみるのもお子さんの気持ちがまぎれるのでおすすめします。
常夜灯などの明かりをつける際には、LEDの白い昼光色は避け、オレンジ暖色の電球色ライトにしましょう。もう少し暗くした時には、布などを被せると明るさを調節できますよ。
パパのスマホの明かりにも注意を
寝室の明かりを一通りチェックしても、パパがスマホをいじっていたら台無しに。
寝かしつけ中ついつい見たくなってしまう気持ちも分かります。
しかし、スマホのブルーライトは、お子さんの大切な目にも影響を与えてしまうのでスマホは見ないようにしましょう。
外の明かりが漏れていないか確認しよう

遮光カーテン・遮光シートを導入
電気を消して真っ暗にしていても、カーテンから車のライトや街灯などの光が漏れていませんか?
先ほどお伝えしたように、子ども(とくに赤ちゃん)は大人より明かりに敏感です。寝つきが悪かったり、泣いたりしてしまうことの原因になっていることも。
遮光カーテンや遮光シートを導入することで、外からの刺激が弱まり、スムーズな入眠の手助けになります。
また、お子さんの睡眠トラブルで、朝の4時や5時にお子さんが目を覚ましてしまい早起きすぎて悩んでいる方も多いです。特に夏場は日が昇る時間も早く、カーテンから漏れてくる日の光に反応して早く目覚めてしまいます。
この場合も遮光カーテンに変えることで規則正しい生活リズムを整える手助けになります。
起床時間になったらカーテンや窓を開けて気持ちの良い朝日を入れ、優しく起こしてあげてくださいね。
遮光等級にも注目
遮光カーテンには、「1級」「2級」と遮光性の等級があります。
その中でも、1級遮光は99.99%以上の光をカットできるのでおすすめです。1級遮光は、昼間でも部屋が真っ暗になるレベル。
遮光カーテンの上下左右の隙間から光が漏れてしまう場合は、カーテンボックスにカバーを取り付けたり、クリップやガムテープ等で留めると効果的ですよ。
優しい音色の音楽や自然音を流してみよう
音楽の力で心が落ち着く
大人でもゆったりとしたオルゴールや波の音、小鳥のさえずりなどの音楽を聴くとウトウトしてしまいますよね。五感に敏感な赤ちゃんや幼児は、優しい音色の音楽を入眠前に聴くことで副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらします。
アプリや音楽プレイヤーでもOK
最近ではスマートフォンアプリにもたくさんの癒しの音楽があります。
わざわざオルゴールのCDを購入しなくても、すぐに用意することができますよ。
保育の現場でもよく使われている、ディズニーやスタジオジブリ、童謡のオルゴールなど、お子さんになじみのある曲がおすすめ。
オルゴールの曲に反応しすぎてしまうお子さんには、ホワイトノイズや波の音、森の中の小鳥の鳴き声などの自然音もおすすめです。
ホワイトノイズとは、テレビの砂嵐のような音のことです。周りの生活音をかき消す効果があるので、寝室に外からの音や生活音が響いてしまう場合にも効果的です。
ぜひお子さんのお気に入り音楽を見つけてみてください。
ボリュームは小さめに
音楽の音量は大きすぎるとかえって興奮してしまいます。
お子さんが気にしすぎないように、“聞こえるか聞こえないかくらい”のボリュームが良いでしょう。
お子さんの可愛いおしゃべりがなかなか止まらない際には、音楽を小さめに流して、「あれ?静かにするとなにか音楽が聞こえてくるよ?」と声を掛けるとパッと静かになりますよ。
毎日同じ音楽を流すのがおすすめ
毎日違うプレイリストや音を流すよりも、固定の同じ音楽を流す方が「この曲が流れたら寝る時間だ」「この曲を聴くとなんだか眠くなってくる」などお子さんにとって入眠儀式の一部にもなります。
寝かしつけの曲や、子守歌で歌っている歌をみんなで共有することで、ママ以外のパパや保育士さんが寝かしつけをする際に役立ちますよ。
温度・湿度を快適にしよう

春夏秋冬で異なる室温目安
一般的に赤ちゃんや幼児にとって理想の室内温度と湿度は、次の通りです。
- 春:20 ~ 22 ℃
- 夏:25 ~ 28 ℃
- 秋:20 ~ 22 ℃
- 冬:20 ~ 25 ℃
- 湿度:50 ~ 60 %
部屋の温度と湿度を快適にすることは、長く良質な睡眠をとる上で欠かせません。
温度計を寝室に置き数字で確認することでより温度湿度を意識化する手助けになるでしょう。
ただし、大人と同じで「暑がりな子」「寒がりな子」もいますので体を触って冷たくないか、熱くないか、背中に手を入れてみて汗をかいていないか確認することも大切ですね。
暑がっているサイン
- 顔が赤くなっている
- 背中、おなかに汗をかいている
- 首や顔周りが熱い
- 髪の毛が汗で湿っている
寒がっているサイン
- 背中、おなかがひんやり冷たい
- 顔色や唇の色が青ざめて見える
特に赤ちゃんは手足で体温調節をしているため、触る場所は体の中心部である背中やおなかで確認するとよいでしょう。
パジャマや寝具も通気性の良いものを
子どもは大人よりも暑がりで、汗っかきです。
特に寝ている間には背中に汗をかきやすいため、通気性の良い素材のパジャマや寝具を用意しましょう。
綿100%・ガーゼ素材のパジャマがおすすめですよ。
特に汗っかきなお子さんには汗取りパッドとの併用も効果的です。
汗を吸わない素材だと、ムレて不快で夜中に目を覚ます原因になることも。
あせもにもなってしまうため、お子さんの肌を守るためにも注意したいですね。
お気に入りの寝かしつけアイテムを用意しよう
「これがあれば安心」という存在を作る
お子さんにとって、お気に入りのアイテムがあることで安心して入眠がスムーズになります。
例えば、「ぬいぐるみ」「ハンカチ」「ガーゼタオル」「毛布」など。
日常の中で気が付くといつもお子さんが手にしているアイテムや、眠くなると触っている素材などありませんか?
お気に入りのアイテムがないか普段の様子からチェックしてみてください。
しかし、お子さんによってはお気に入りの安心アイテムが見つからない場合ももちろんありますよね。そんな時は、肌触りの良いアイテム(さらさら、ふわふわ、モフモフ…)を用意し寝かしつけの際そばに置いてみてください。
特にパパが慣れない寝かしつけするときこそチャンス!ママがいない不安な中、安心アイテムを生み出すきっかけになりますよ。
保育園や旅行先でも役立つ!ねんねアイテム
私は現役保育士ですが、0、1、2歳児クラスでは入園してまだ慣れない頃に安心アイテムがあるか保護者の方にお聞きします。安心アイテムを園でも持つことで、よりスムーズに園生活に慣れることができるかもしれません。そんなときを見越して、園にも持っていける「ハンカチ」や「タオル」から安心アイテムを見つけるのもおすすめです。
また、ねんねアイテムがあることで外出先や旅行時にも持参すれば、いつもと違う環境での安心材料にもなりますよ!
安全面にはご注意を
寝かしつけにつかう安心アイテムは、口に入れても安心な素材やパーツなど取れてしまう危険性のないものを選びましょう。
特に0歳1歳のお子さんは窒息に注意が必要なので、入眠したらぬいぐるみやタオルなどはそっと離してあげましょう。
寝室には余計な刺激は持ち込まないように
おもちゃやタブレット等は入眠の妨げに
寝室におもちゃやタブレットなどがあると、お子さんは「遊びたい」という気持ちが勝ってしまいます。

確かに。寝る時間なのにおもちゃで戦いごっこが始まったり、絵本がたくさんあって何冊も読んでと言われたり…
おもちゃは寝室から無くして、絵本はその日に読む本だけ置くようにするといいんだね!
おもちゃ等遊ぶものは持ち込まず「寝室はねんねの場所」として整えることで、お子さんも気持ちの切り替えがスムーズになりますよ。
寝室に置くものはシンプルに
それでは具体的にどんなものを置くと良いのでしょうか。
- ベッド・布団・ベビーベッドなどの寝具
- その日に読む絵本
- お気に入りのねんねアイテム
- オルゴールなど音楽を流すグッズ
- 加湿器や空気清浄機
このように余計のないものがないほど、寝ることに集中することができます。
0・1歳のころはベッドから寝返りして落ちてしまう危険性もあるため、ベッドガードも取り付けると安心です。
間取り的に寝室がない場合は?
昼間リビングや子ども部屋として使っている部屋に、布団を敷いて夜は寝室としているご家庭もありますよね。
そのような場合は、おもちゃをしっかり片付けてお部屋を一度リセットすることでお子さんの意識も変わりますよ!
寝かしつけに関するママの本音・パパの本音
入眠しやすい寝室環境のポイントをご紹介しましたが、最後に寝かしつけに関するママの本音・パパの本音をご紹介します。私自身も感じたことや、ママ友から聞いた話、保育士として働く中で保護者の方からお聞きしたお話で多かった声です。
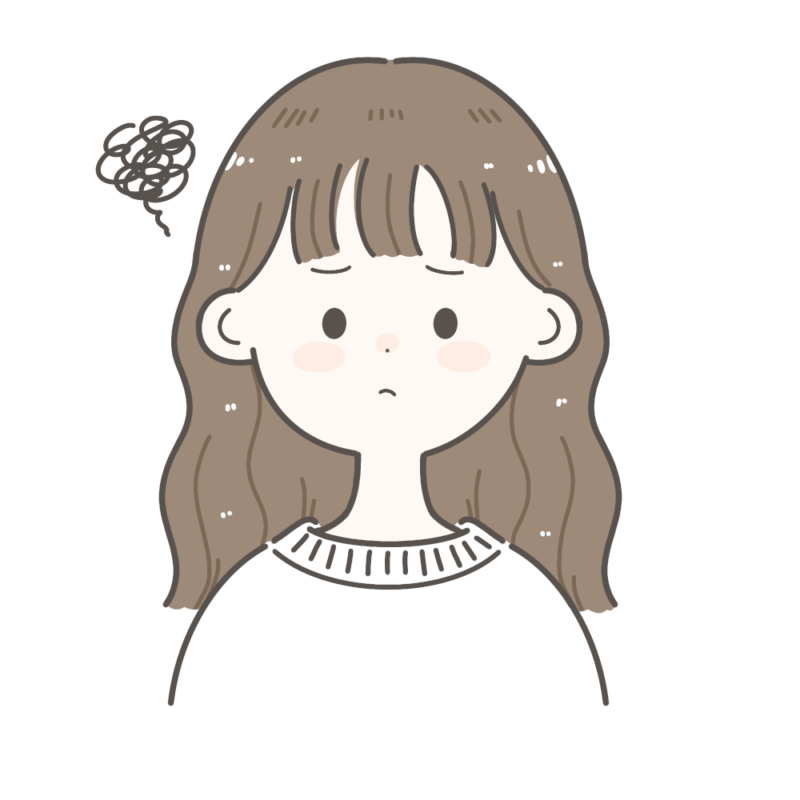
- パパが寝かしつけしてくれれば、その時間に家事や通園準備が出来るのに…
- 家事や育児、仕事に疲れていつも子どもと寝落ちの日々…私だって夜の静かなリビングで自分時間を楽しみたい!
- パパに寝かしつけを頼むと子どもが私を求めて泣いてしまってなんだか罪悪感。
- 「俺じゃ寝てくれない!ママが寝かした方が早いじゃん!」とパパは言うけれど丸投げしないで欲しいな…
- 夜間授乳で何度も起きて心身ともにヘトヘト…パパにもう少し労わって欲しいな。

- 慣れてるママが寝かしつけした方がスムーズなんだけどな…
- 仕事で疲れてるし帰宅後はゆっくりしたいな。
- ママが寝かしつけしてる間に家事をやってみたけど、ダメ出しされるし…
- 俺が寝かしつけすると子どもが嫌がるから傷つくんだよな…
- 夜泣きで起こされてるのはママだけじゃない!
- 俺だって寝かしつけできるようになりたい!
「あーそれ分かる!」と共感していただける部分もあったのではないでしょうか。
家事、育児、仕事を日々頑張っているパパ、ママ。寝かしつけの悩みや、夜泣き、早朝起きなどの睡眠トラブルがあると心身ともに疲れてしまいますよね。そんな時こそ、何か解決の手立てはないか模索しながら、お互いに労いの言葉を掛け合いながら支えあって一緒に子育てしていけるといいですね。
寝室環境を整えてスムーズな入眠を

以上がスムーズな寝かしつけのための寝室づくりのカギとなります。
- 寝室は真っ暗にする
- 遮光カーテンや遮光シートを導入
- 優しい音楽で心をリラックス
- 温度湿度を整えて快適に
- ねんねアイテムを用意して安心感を
- 余計な刺激物は持ち込まない
寝かしつけに関するポイントは数多くありますが、今回は寝室づくりについてまとめました。赤ちゃんのねんね期から寝返りを打ち始める頃には、落下防止についても早めに対応してけると良いですね。
お悩みの改善策の一つとして、寝室の環境を整えることがお子さんにとって問題解決の糸口になることも。
すぐにチェックできることばかりなので、ぜひパパが率先して寝室環境を見直し、試してみてくださいね。
