パパの読む絵本が1番大好きになる読み聞かせテクニック・絵本の選び方【保育士解説】

お子さんとの触れ合いの中で最も身近な“絵本の読み聞かせ”
泣いている子も絵本であっという間に気持ちが切り替わったり、様々な興味も広げられたり、絵本はとても素晴らしいものです。一方で、
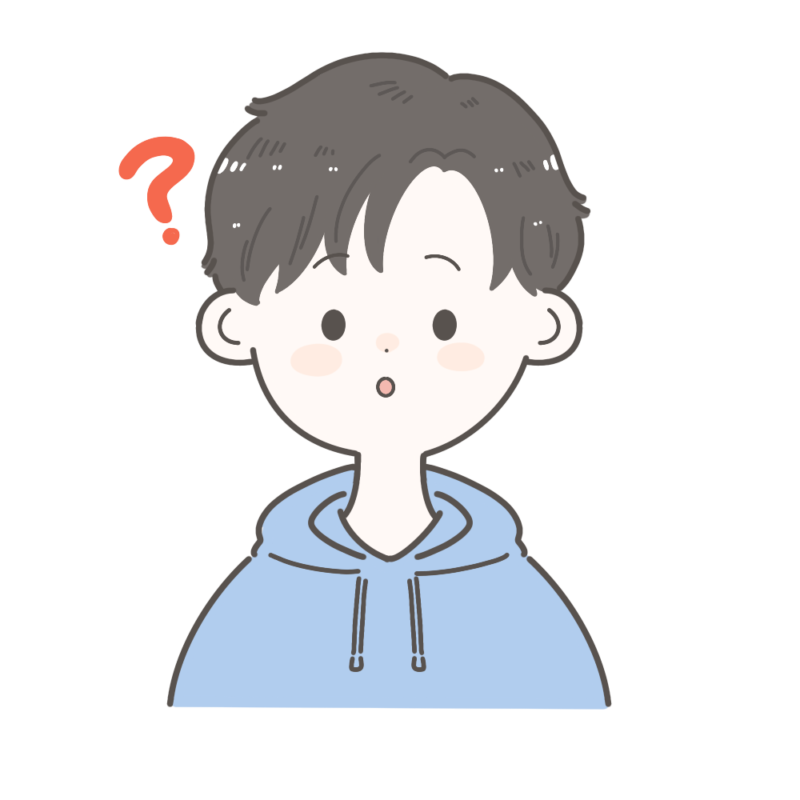
絵本ってどんなものを読めば喜ぶんだろう?
いつもワンパターンな読み方になって飽きられちゃうんだよな…
という読み聞かせについて、苦手意識やお悩みを抱えている方も多いです。
この記事では、現役保育士ママが絵本の読み聞かせついて情報をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。
ぜひお子さんとの絵本時間を、ひとつのコミュニケーションとして楽しんでみてくださいね!
絵本の読み聞かせは入眠ルーティンにおける大切な儀式です。
寝かしつけ全般の進め方についてはこちらでまとめていますので、あわせてご覧ください。

パパの読み聞かせはメリットがたくさん!
パパは普段からお子さんに絵本の読み聞かせをしていますか?
実は、パパが絵本の読み聞かせを行うことで、親子ともに大きなメリットがあります。
- パパが読んでくれることで得られる特別感・幸福感がある
- ママと異なるパパの声のトーンや話し方が良い刺激になる
- 男性ならではの表現や読み方がおもしろかったり、興味を引いたりする
- パパと子どもの絆を深め、安心感や愛情を感じる
- 忙しい日々の中で絵本を読むひとときがかけがえのない親子時間になる
- 子どもの語彙力や表現力、理解力の高まりを実際に感じられる
- 子どもの素直で様々な反応を間近で見ることが楽しみとなり、子育てのやりがいを感じられる
- 読み聞かせを通してパパ自身の表現力や語彙力や様々な分野の知識が増え、多くのスキルが磨かれる
- パパ自身が積極的に育児に関わることで、ママからの信頼度が高まる
このように、パパが絵本の読み聞かせをすることは単なる役割ではなく、それ以上の大きな価値があるのです。
絵本の読み聞かせはいつから?

いつからでもOK
「産まれて数カ月の赤ちゃんにも絵本読むの?」と思うパパも多いかと思いますが、ひとつのコミュニケーションツールとしても絵本の読み聞かせは有効です。
大好きなパパの声を抱っこされながら聞くだけでも赤ちゃんとのスキンシップになりますよ!
絵本を見つめだすのは4,5カ月から
実際に絵本のイラストを目で追ったり見つめたりするようになるのは生後4,5カ月頃からです。赤ちゃんの月齢が進むにつれて絵本を見て笑うようになったり、お気に入りのページが出てくるようになったりします。
読み聞かせで得られる効果
絵本の読み聞かせを通して様々な良い効果をもたらしてくれます。
お子さんにとって絵本で育まれる心や力は絶大なものなので、ぜひ知っておくと良いでしょう。
高まる力とは?
最後まで絵や話を観察する
絵本を読むことで集中力が高まります。小さい頃は短い簡単なお話から始まり、年齢を重ねるごとに長いお話も最後まで集中して見られるようになります。いきなりは難しいので、日々絵本と触れ合う時間が大切です。
様々な表現や言葉に触れる
絵本には様々な表現や、言い回し方、言葉が出てきますね。
日常会話の中では出てこないような言葉に触れられます。小さい頃にはイラストを見て名前を覚えたりも出来ます。
話の内容や文脈を理解する
絵本の読み聞かせを通して、子どもはお話の内容や文脈を理解する力を養うことができます。登場人物の感情を読み取ったり、お話の流れを理解することで読解力が高まります。文章を読み取る力が向上することで、学校での勉強の内容を理解したり読み解く力に繋がっていきます。
育む心とは?
好奇心を育む
「なんで?」「どうして?」「これは何?」と絵本の内容に興味を持つことで、好奇心が大きく成長します。好奇心はその後の勉学の基礎となる大切な部分ですので、お子さんの疑問に思ったことや、興味のあることを大切にしてあげたいですね。
感受性豊かになる
登場人物に共感したり、反感を抱いたり、悲しい気持ちになったり、嬉しい気持ちになったり…様々なお話を通して感情移入していくことでお子さんの感性が豊かになります。人間関係を築いていく中でも、他者への共感力が育まれることはとても大切な力となります。
情緒が落ち着く
読み聞かせの時間は親子での心地よい時間となり、情緒が安定したり、様々な登場人物の感情を知ることで自分の感情をコントロールする手立てになります。
コミュニケーション
パパとの触れ合い
大好きなパパに大好きな絵本を読んでもらう、子どもはそれだけで笑顔になり、嬉しく感じてくれます。パパとの触れ合いを通して、信頼関係も築いていくことができます。
読み聞かせのコツ・方法を保育士ママが解説
さあ、いよいよ読み聞かせのコツとポイントを現役保育士ママである筆者の経験を活かし、ご紹介していきます。
ちょっとした工夫で、お子さんの興味を引くことができたり、絵本に夢中になったりする。お子さんの反応を楽しみながらぜひ読んでみてください。
絵本の持ち方
見やすい位置で絵本を持つ
意外と見落としがちなのが持ち方。
お子さんが見やすい位置で、手で絵を隠さないよう注意しましょう。
絵本を動かさない
絵本の位置を動かしてしまうとお子さんの集中力の妨げになってしまいます。
しかし、絵本の内容によっては、左右に揺れてリズムを楽しんだり、動きを付けることでより楽しめたりするようなものもあります。絵本の内容に応じて変えてみてください。
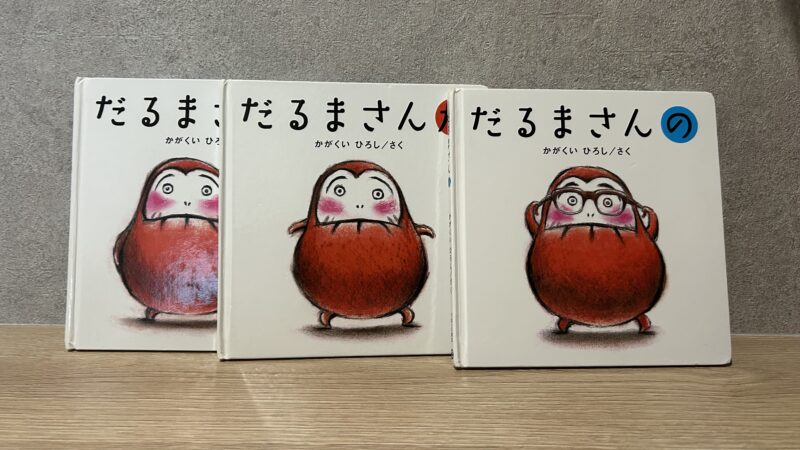
「だるまさん」のシリーズは左右に絵本も身体も揺らして読むと楽しさ倍増です。
座る位置を壁側にする
これは保育現場でよく気を付けられているポイントです。
絵本の後ろ側はできるだけシンプルな壁にすることで、集中して最後までお話を聞くことが出来ます。絵本の後ろ側が通路で人の動きがあったり、好きなキャラクターの絵が貼ってあったりなどすると集中力の妨げになります。寝かしつけ前には、布団に仰向けに寝転がって読むのも良いでしょう。
絵本の読み方
子どものペースに合わせて読む
お子さんの年齢にあったペースで読みましょう。早すぎると内容に付いていけなかったり、ゆっくりすぎると飽きてしまいます。
抑揚を付けて読む
話の展開やキャラクターの感情に合わせて抑揚をつけて読んでみると、食い入るようにお話に引き込まれ、絵本の世界がより楽しくなります。
- おじいさん、おばあさんはゆっくりと、子どもは早口で話す
- びっくりする場面では大きな声で、悲しい時は小さな声で話す
- 展開が早い場面は、ページをサッとめくる
- じっくり展開を予想してわくわくする場面は、ページをゆっくりとめくる
声色を変えて
声色を変えることで “誰が喋っているのか” が分かりやすくなります。
ぜひパパもお話を楽しみながら、どんな声で読めばキャラクターのイメージに近づけるか試してみて下さい。
- おじいさん、おばあさんはしゃがれた声で話す
- 子どもや小動物は高い声で話す
- 悪者は低く唸るような声で話す
文章を省略・変更しない
絵本はプロが製作しています。
言葉のチョイスや、響き方、ページの文章の間(マ)など考え尽くされていますので、文章を省略したり、変更しないようにしましょう。
特に、小さな赤ちゃんは絵本に出てくる言葉が魔法のように面白くて、たくさん笑ってくれますよ!
絵本を読むときの心構え
絵本を読む上での心構えをご紹介します。
たくさんポイントがあって難しい…と感じているパパは、こちらを押さえておくだけでも良いでしょう。
同じ絵本を繰り返し読んでもOK
お子さんに読み聞かせを行っていると、だんだんとお気に入りの絵本が出てきて、何度も「これ読んで!」と持ってきてくれます。
「え~またこの絵本?」と思うパパも多いかと思いますが、繰り返し何度でも読んであげてOK。
子どもなりに、お話の展開が好きだったり、登場人物が好きだったり、言葉のチョイスが好きだったり…と理由があります。
お子さんの“読んで!”に応えてあげることで、自己肯定感や満足感にも繋がります。
反応を楽しみながら自分も楽しんで
絵本を読んであげるとお子さんはどんな表情や反応を見せてくれますか?
ケラケラ笑って楽しんでくれたり、感情移入して悲しくなっていたり…様々な反応を見せてくれることでしょう。
「この絵本読んで!」とパパの元に持ってきてくれるのは子育て期間ずっとではありません。そんな貴重なかけがえのない親子時間をパパも思い切り楽しんでみて下さい。
パパが楽しんで絵本を読んでくれるのと、イヤイヤ読んでくれるのでは、お子さんの反応も変わりますよ!
読み聞かせ中に質問や説明をしない
ついつい「これはどうしてだと思う?」などとお子さんの考えを聞いたり、難しい内容には説明を加えてしまいたくなります。
お子さん発信の質問には、答えてもOK。パパ発信の質問や説明は控えましょう。
絵本のスペシャリストが作成した絵本ですので、余計なことは付け加えないようにしましょう。
【年齢別】絵本の選び方
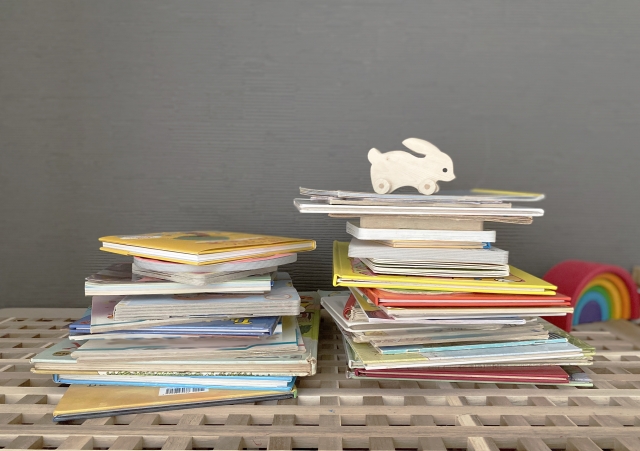
続いて、絵本の選び方についてご紹介します。
お子さんの年齢や成長に合った絵本を選ぶことで、絵本への興味関心がより深まります。
成長に合わせてお子さんに適した内容の絵本を選ぼう
0歳・1歳は頑丈で色合いがはっきりした絵本

✔ 色合いがはっきりしていて分かりやすい
✔ 短い文章
✔ 繰り返しのフレーズが楽しい
✔ 頑丈な絵本
✔ 触って様々な感触を楽しめる絵本
言葉が分かりやすく、繰り返しのフレーズがあるなど響きが面白いもの。絵ははっきりした色合いや分かりやすいものがおすすめです。
赤ちゃんや1歳のお子さんは、五感をフル活動させながら「これは何だろう?」「なんだか楽しいな!」と絵本を楽しんでくれます。
触るとふわふわやチクチクなどの感触を味わえる仕掛け絵本も良いですね。
この時期は絵本を破いてしまったり、かじってしまったりするため、丈夫で安全なものを選びましょう。
2歳は生活に寄り添った簡単な内容の絵本
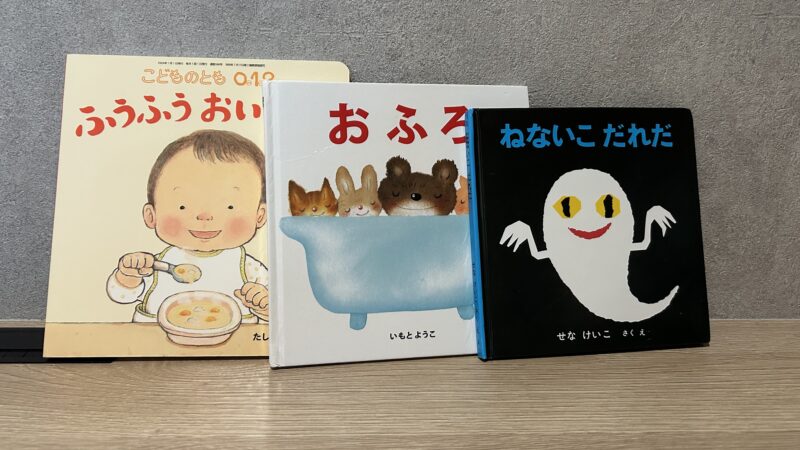
✔ 内容が分かりやすい
✔ 生活に寄り添った(ねんね・トイレ・食事・片付け・歯磨きなど)
✔ 面白い表現の絵本
✔ 身近なものが載っている言葉図鑑
絵本の内容にも関心を向き始める時期です。
分かりやすく端的な内容で、楽しい内容のものがおすすめです。
身近な生活に関する内容は理解しやすく、興味を引きます。
動物や乗り物、食べ物などの身近な言葉が乗っている絵本は語彙力も増します。
3歳はお子さんの好きな分野の絵本
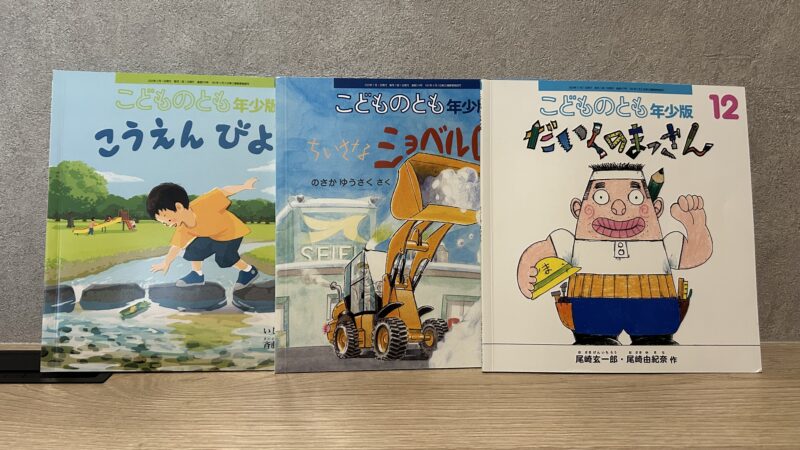
✔ 簡単なストーリー性のある
✔ お子さんの興味のある分野(虫好き・車好き・恐竜好き・宝石好きなど)
この時期になるとお話の内容を理解し、展開を楽しめるようになります。
語彙力や読解力も高まっており、何より好奇心旺盛な時期です。
3~4歳のお子さんは、「もっと知りたい!」と好奇心から自分の興味のある分野の絵本を選ぶことも多くなります。
4歳は社会性のある内容の絵本
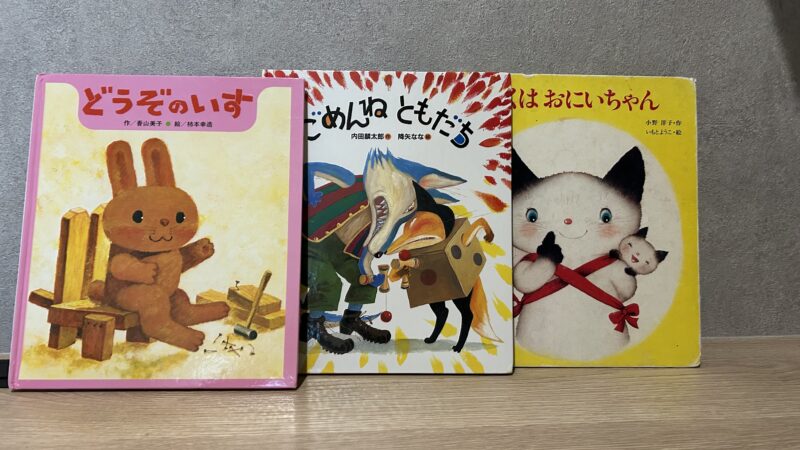
✔ ファンタジーや冒険もの
✔ 社会性のあるもの
✔ お子さんの興味のある分野(虫好き・車好き・恐竜好き・宝石好きなど)
しっかりしたストーリー展開のものを楽しめます。
ファンタジー要素のあるものはハラハラ・ドキドキしながら展開を予測し、楽しむことができます。登場人物の様々な感情に触れることで、日常生活で友達の気持ちを考えるきっかけにもなります。
5歳は内容のある長いお話の絵本
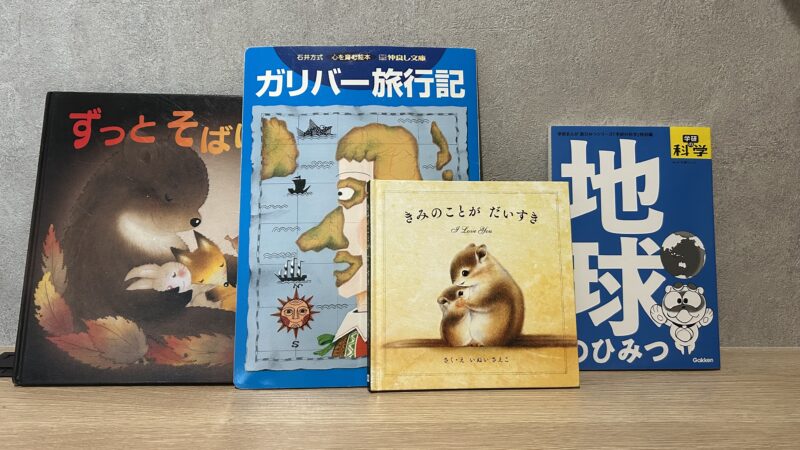
✔ 長いストーリー
✔ 絵の少ない童話も
✔ 一つのお話を数日間掛けて読んでもOK
✔ お子さんの好きな分野を深堀り
この時期には日々色々なことを体験したり、様々な感情を経験したりして心も身体も大きく成長する時期です。
集中力や好奇心も高まっているので、絵が少なくて長いお話の内容にも興味を持つようになります。長い冒険ものの絵本などを数日に分けて読むこともできるように。
この時期にはお子さんの興味のある分野、全く興味のない分野がはっきりしてきますので、興味関心に合わせて選ぶと良いでしょう。
【目的別】絵本の選び方
寝かしつけをスムーズにしたい時
寝る前の絵本タイムは、お子さんにとって分かりやすいねんねルーティンです。
お子さんが選んだ絵本を一緒に読むことで、安心感や幸福感も増します。
さらに、絵本の中には“寝る”ことを題材とした内容も数多くありますので、寝かしつけ時に読むことで効果倍増!スムーズな寝かしつけに役立ちます。
迷った際には、絵本の最後をチェックしましょう。
「おやすみなさい」「また明日」などの一日の締めくくりの言葉が添えられている絵本は“ねんね”をテーマにした絵本であることが多いですよ。
季節感や年中行事の楽しさを感じて欲しい時
日本には春夏秋冬の美しい四季や、昔ながらの行事があります。
絵本を通して季節感に触れることができ、より四季を身近に感じられるようになります。
春にきれいに咲くお花やこいのぼり、夏は暑いから水遊びや夏祭り、秋においしい食べ物やお月見、冬はクリスマスやお正月に豆まき…など。季節や行事に触れ、実際に感じることでたくさんの感動や発見を味わうことができますよ。
四季を味わうことで情緒が安定したり、日々の暮らしを楽しむことができるようになります。
ぜひ季節やイベント行事に合わせた内容の絵本を選び一緒に読んでみてください。
こころの育ちを助けたい時
お子さんが表現する嬉しい・悲しい・怖い・びっくり・嫌な気持ち・怒り。
“様々な感情表現があっていいんだよ”ということを伝えるには、絵本が最適です。
主人公に感情移入してたくさんの感情に触れることができます。
保育の中でも、“感情の表現・理解”をテーマにした絵本を選び、読むことも多いです。
例えば、「最近友達同士の喧嘩が多いから、今回は喧嘩して仲直りするお話をみんなに読もう」「仲間に入れてもらえず寂しそうな子がいたから、皆で遊ぶ楽しさを感じられるような絵本を読もう」など。
降園前に読む絵本は、一日の保育の中を振り返りながら身近なテーマの絵本を選定し、子ども達の心に届くよう願いを込めて読んでいます。
生活習慣を身に着けたい・見直したい時
手洗い・トイレ・歯磨き・あいさつ・お風呂・食事・お片付け…
お子さんにとって身近なテーマですよね。
実際の生活にリンクさせることで、絵本の効果倍増です!
「さっきの絵本みたいにトイレ行ってみようか」「この絵本のカバさんみたいに大きな口で歯磨きできるかな?」など、生活の中に絵本を取り入れてみると、育児のお悩みが解決できるかも。
語彙力を伸ばしたい時
おしゃべりし始めたころや、言葉に興味を持っている時期には、たくさんの単語と、それに結びつくイメージが載っているものがおすすめ。
ものの名前(食べ物や乗り物、動物など)が載っていたり、おもしろい擬音語(どんどん・ざーざー・ツンツンなど)が載っていたり。絵本によりさまざまな言葉や表現の方法を吸収することができ、会話の幅も広がります。
絵本を読むタイミングは?
いつでもOK
絵本はいつ読んでも良いものです。
保育士として働く中で実際に絵本を読むタイミングの例は次の通りです。
- 活動前に少し落ち着いてほしい時に絵本を読む
- トイレ前に、トイレに関する絵本を読むとスムーズに向かえる
- 片付けがなかなか出来ないときに、片付けに関する絵本を読む
- お昼寝前にゆったりとした雰囲気の中、絵本を読んで落ち着かせる
場面に応じて生活の中に絵本読み聞かせを取り入れ、視覚的に子ども達に伝えることでその後の行動は大きく変わります。
寝る前に落ち着いた雰囲気で

保育現場でもお昼寝前に絵本の読み聞かせが定番です。
夜の寝かしつけ前にゆったりとした雰囲気の中、読み聞かせを通して親子で触れ合うことで安心して入眠できます。
ぜひ寝る前に絵本読み聞かせのルーティンを取り入れてみてくださいね。
もう寝る時間なのに「もっと読んで!」の対処法をご紹介
時間に限りがないときは、いくらでも読んであげたい絵本。
しかし寝る時間が迫っていたり、お出かけしなきゃいけない時など、お子さんの「もっと読んで!」に困ってしまう時もありますよね。
事前に読める冊数を伝えてから選んだのに…エンドレスで終わりが見えない…なんてこともよく聞く話です。
そんな時におすすめな声掛けは次の通りです。
視覚的にも先の見通しを持つことが出来て安心感につながる。
“明日、〇〇ちゃんに読む絵本” などお簡単なメモ書きを貼り付けるだけでお子さんにとっては特別感を得られる。
しおりなどを絵本に挟むことで、絵本のお約束に対する特別感につながる。
お子さんが絵本の読み聞かせの終わることに「寂しい」と感じる気持ちを、次も読めるワクワクに変えてあげるのがポイントですよ!
親子で心地よい絵本タイムを…
以上が、絵本読み聞かせを子どもが大好きになる方法でした。
- 絵本は赤ちゃんからでもOK
- 読み聞かせは親子のコミュニケーションツールになる
- 読み方には様々なポイントがある
- 年齢・興味・季節に合った絵本を選ぶ
- 寝かしつけルーティンに取り入れる

絵本の読み聞かせはたくさんのメリットがあって、豊かな心を育むことができるんだね!今まで棒読みになってしまってたけど、上手に読むポイントも実践してみるよ!
ぜひ、お子さんの反応も楽しみながらパパも楽しんで素敵な読み聞かせ時間を過ごしてくださいね。
